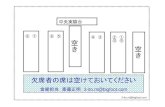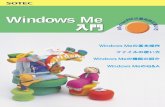(Selbstbesinnung)としての陶冶― - Kansai Uikuoyama/lecture/paper/...1...
Transcript of (Selbstbesinnung)としての陶冶― - Kansai Uikuoyama/lecture/paper/...1...

1
ディルタイの陶冶 (Bildung)概念について
―表現を経由する「自己省察 (Selbstbesinnung)としての陶冶―
瀬戸口 昌也
(大阪教育大学教員養成課程 学校教育講座 准教授)
はじめに
ディルタイ (Wilhelm Dilthey,1833-1911)はその教育学の中で陶冶について、次のように述べて
いる。「われわれが陶冶する(Bilden)と呼ぶものは、心的生の諸過程とそれらの結合の完全性
を確立しようと努めるあらゆる活動であり、こうして達成された完全性を陶冶と名づける」(Ⅵ
70)1。ディルタイはこのような陶冶概念を基に、彼独自の教育学理論を体系的に展開している
が、その背景を二つ指摘することができる。一つは彼が「心的生(Seelenleben)」と呼ぶ人間の
生の心理的側面が、「目的論(Teleologie)」的性格を持つという彼の心理学であり、もう一つは
彼が当時直面していたドイツの教育改革という歴史的状況である。これまでのディルタイの教
育学研究において、この二つの背景については必ずしも十分に考察されてはこなかった。心的
生の目的論に関して言えば、彼の教育学で重要な位置にあるこの概念が、教育学以降の精神科
学の基礎づけの構想の進展の中でどのように展開していったのかが考慮されないままであり、
また教育改革の問題に関しては、この実践的問題がディルタイの教育学理論の体系とどのよう
に関連しているのかが十分に考察されることがなかったのである。このような理由からディル
タイの教育学は現在でも、彼の著名な論文『普遍妥当的教育学の可能性について』(1888 年;
以下『教育学論文』と略記)を基にして、教育学の普遍妥当性の限界について論じた教育学の
古典という一般的評価に留まっているように思われる。
本研究はこれまで注目されることのなかったこの二つの背景からディルタイの教育学を考
察して、ディルタイの陶冶概念と教育学が持つ現代的意義を明確にすることを目的とする。そ
のためにまず、教育学における陶冶概念一般の歴史について記述し、陶冶概念の変遷とそれに
基づく現代教育学の陶冶研究の傾向を明らかにする。次にこの傾向から、ディルタイの教育学
の内容について批判的に検討する。さらにディルタイの陶冶概念と教育学理論の内容を、彼の
精神科学の基礎づけの構想全体の発展と、教育改革という二つの観点から分析する。この分析
からディルタイの陶冶概念の発展と、彼の教育学の内容の歴史的制約性と言えるものが明らか
になる。最後に、このようにして明らかになったディルタイの陶冶概念と教育学理論について、
再度現代教育学の陶冶研究の傾向から検討し、その現代的意義について考えることにする。
ドイツ教育学における陶冶研究の歴史
Bildung の概念は、ドイツ教育学の基本概念として長く使用されてきた歴史を持つ。日本で
は「陶冶」、「教養」、「人間形成」等と訳されるこの概念は、一般に人間性の調和的発展を
目指すフンボルトの新人文主義的な「一般的人間陶冶 (allgemeine Menschenbildung)」の理念に

2
代表されるものとして理解されてきた2。しかし Bildung の語はフンボルト以前にも古くから使
用されており、また現代のドイツ教育学においても Bildung は Bildsamkeit(陶冶可能性)とと
もに、その歴史や意味や研究方法についてはもちろん、哲学や心理学や社会学の領域と関連づ
けられて考察の対象になっている。
Bildung は本来、神学的・神秘主義的な「神の似姿としての自己完成」 3の意味で用いられて
いたが、それがドイツ教育学の専門用語として取り入れられるようになったのは、18 世紀中頃
からとされる 4。教育学の分野では陶冶概念は、当時のカント、フィヒテ、ヘーゲルらの哲学体
系の影響下で教育学における「哲学的反省」の対象として把握され、さらに 19 世紀にヘルダ
ー、フンボルト、シラーらによって古典的で新人文主義的な陶冶概念として発展したものとさ
れる。それ以来教育学は、陶冶を哲学的に反省する学問と見なされるようになるが、この見方
が批判され、大きく変化したのは 20 世紀になってからである。具体的にはそれは 1960 年代で
あり、その背景としてガウスは次のような要因を指摘している 5。第一にロートの著作(1962
年)に象徴されるように、教育学研究における「実証主義的転回(realistische Wendung)」が(特
に当時の精神科学的教育学に対して)提唱されたこと、第二に「1968 年運動」と呼ばれる当時
のドイツの社会的政治的運動を背景に、社会学が特に社会批判理論として指導的役割を果たす
ようになったこと、第三に歴史学が、当時主流だったテクスト解釈に基づく人物史の解釈学的
処置から、社会学との対決の中で、社会の歴史記述の構造史的処置へと向かったこと、第四に
クーンの「パラダイム転換」(1962 年)に象徴されるように、科学理論の歴史が長期的継続的
進歩はとらずに、「科学の共同体」の中で「突発的」変化をとるものと見なされるようになっ
たこと、である。
1960 年代のこのような状況の中で、1970 年代以降の教育学における陶冶研究は、それまで
の伝統的な哲学的反省から距離を置こうとする。この傾向は陶冶の歴史的研究の分野では、例
えばそれまでの国家的な教育制度や教育機関の歴史を研究対象とするような「教育学の歴史か
ら歴史的陶冶研究へ (Von der Geschichte der Pädagogik zur historischen Bildungsforschung)」(テ
ノルト)6という言葉で表現されるように、新たな理論と方法論の模索へと向かわせることにな
る。ガウスによれば、この歴史的陶冶研究は二つの方向を取ったとされる。一つは「歴史的社
会化研究 (historische Sozialisationsforschung)」であり、もう一つは「歴史的人間学 (historische
Anthropologie)」である 7。両方向はともに共通して、教育をシュライアーマッハー以来の伝統
的な問い―「教育的関係の中での諸々の世代の志向」―に置くことはしない。両者が関心を持
つのは、「社会的及び文化的な諸関係の中で、教育的なものの組織的な諸形式を結びつけてい
くこと」である。その際歴史的社会化研究は、社会的諸関係の中での機能性に注目して、社会
変化についての社会学的及び社会史的理論へと遡及していく。それに対して歴史的人間学は文
化的諸関係の中で、文化の解釈とそれに基づく行為がどのように相互依存しているかに注目
し、文化史的・心性史的でポスト構造主義的なアプローチへと遡及していく。これら二つの方
向は、1970 年代から 80 年代にかけて、理論的及び方法論的基礎づけを重ねて行って「学派」
と呼べる一定の立場を形成するようになる8。
1970 年代から 80 年代にかけてのこのような教育学の歴史研究の変化は、陶冶概念をそれま
での哲学的反省から「経験的な陶冶研究」へと向かわせることになった。1990 年代になると、
その橋渡し役として「伝記 (Biographie)」が注目されるようになる。むろん教育学にとって、伝

3
記は陶冶研究と関連して長く重要視されてきたものであり、後述するようにディルタイや、そ
の弟子のミッシュにおいても重要な研究対象とされてきた。しかし両者が個人の生涯を精神史
の観点から記述しようとしたのに対し、1990 年代の伝記研究は「社会的及び主体的経験の摂取
(Verarbeitung)の個人的諸形式を、物語的インタビューと経験的な質的研究によって跡づける」9ことを特徴とする。こうして 90 年代には陶冶概念とその理論は、「経験的な」伝記研究の観
点から見直されていくことになる。伝記研究は「経験的陶冶研究」としてその研究領域やテー
マ、方法を多様に展開していく。例えば 90 年代に特に心理学と社会学で重要な位置づけを得
るようになった行為理論の観点から、伝記研究はより厳密に、行為を制約している社会的制度
的側面に注目した「生活史(Lebenslauf)」研究と、個人の行為の反省を通して主観的に構成
される「伝記」研究として区別されたり、アメリカのブルーナーの「民族心理学」に基づく物
語論との関連で注目されたりもしている10。
このような経過を経て、2000 年以降も陶冶概念は依然として多様な観点から議論され続けて
いる。エーレンスペックによれば、現在陶冶を概念的に論じる場合、その内容は次の五つの次
元に区別されると言う11。
⒈個人的な「資産 (Bestand)」としての陶冶。この次元では陶冶は一定の知識の取得と、それ
に裏づけられた能力 (Kompetenz)を得ることを意味する。ここでは学んだ知識の内容が、陶冶の
内実と見なされるのであり、このような見方はいわゆる「実質陶冶理論 (materiale
Bildungstheorie)」と呼ばれるものである。
⒉個人的な「能力 (Vermögen)」としての陶冶。この次元は、いわゆる「形式陶冶理論 (formale
oder funktionale Bildungstheorie)」と呼ばれるものである。この場合、陶冶は学んだ知識の内容
とは関係なく、個人の自己形成を可能にする諸力、能力、適性、完全性、処置などを意味する。
⒊個人的なプロセスとしての陶冶。この次元では陶冶の過程に注目し、陶冶過程を「ダイナ
ミックで、常に具体的かつ個人的な運動」、あるいは「前もって与えられた状態と資産すべて
を残して、継続的に自己を越え出て行くこと」と見なす。このような見方は、陶冶の哲学的反
省の伝統では「陶冶可能性 (Bildsamkeit)」と呼ばれてきたものである。エーレンスペックによ
れば、陶冶可能性は個人の内面での自由な決断と、行為主体としての個人による外的決断との
関係の中で、個人の内的規則に基づいて遂行される「自己陶冶」と見なされ、この意味では「オ
ートポイエーシス」ないしは「自己組織化」の考えに接近するという。(エーレンスペックは
これらの考えもまた、認知心理学的で構成主義的な学習理論との関係で、経験的な陶冶研究と
関連を持つものとされる。)
⒋個人の自己超出と人類のより高い形成としての陶冶。この次元は歴史的には、哲学的及び
宗教的に「神の似姿」への接近として把握されてきた陶冶概念が、1980 年代のポストモダン的
哲学による批判以降、その「世俗化された型」として残存しているものとして理解される。し
たがってその特徴は、人間が神への継続的接近を目指す「進歩思想」の世俗化であり、それは
例えば未来の公正な社会、個人間の円滑な相互行為、平和的で自然と共鳴し合う人間の生き方
(エコロジー的陶冶理論)などを目指す陶冶概念に見いだすことができる。その一方で、この
ような「解放と進歩」という歴史観を批判し、ポストモダンないしはポスト構造主義の哲学(リ
オタール、フーコー、デリダなど)の影響を受けて、陶冶思想の「多元化」の下にその見直し
をはかる陶冶概念も登場した。このようなポストモダン的陶冶概念は、それ以前の陶冶概念が

4
「主体」と「自己同一性」に方向づけられており、その背後には「神への接近」というキリス
ト教的な伝統があることを批判的に問うのである。この場合陶冶概念は、「教育と陶冶研究の
反省機関」として機能し、経験的な陶冶研究を刺激することになる。
⒌陶冶の制度と陶冶する人々の活動性としての陶冶。陶冶が行われる諸制度や陶冶を行う
人々の活動の意義については、シュライアーマッハーやフンボルト、ヘルバルトなどの古典的
な陶冶概念でも指摘されてきたことであり、今日の陶冶研究においてもその重要性には変わり
はない。教育制度には、教育の思考と行為の両者を構成し調整していく原理が働いているもの
とされる。それゆえ教育制度の陶冶論的反省では、個人の陶冶可能性と自己活動という個人的
側面が、どのようにして教育的行為の社会的側面と一致するのか、すなわち個々の実践を関係
づけ、社会的決定を教育的で実践的な決定へと移行させていくような教育制度の調整的側面と
一致していくのかということが問われ、研究されなければならない。制度的な観点からのこの
ような陶冶研究では、陶冶概念は経験的な陶冶研究と相互に結びつく。2000 年以降の国際的な
学力調査 (TIMMS,PISA)の結果は、陶冶と制度と組織との関連を新たに考慮させ、陶冶の「計測
可能性」と「比較可能性」が問題とされるようになった。陶冶は国際的な比較研究を機に、将
来的な「コンピテンシーモデル」の中で把握され、「標準化 (Bildungsstandart)」されて査定さ
れる対象になったのである。
歴史的陶冶研究における歴史理解の方法
以上の考察から明らかなように、陶冶概念は現在さまざまな次元で語られ、その内容に応じ
た理論が形成されている。陶冶は結局「決まっているようで決まらない (bestimmt unbestimmt)」12概念であり、その意味では常に解釈を必要とする「精神科学的概念」(ディルタイ)あるい
は「解釈的概念」(ミッシュ)として特徴づけることができる。陶冶概念とその理論の多元性
に応じて、教育の歴史研究から発展した歴史的陶冶研究においても、歴史理解の方法は多様な
ものとなる。ガウスは歴史理解の方法を、次の三つのモデルに区別している13。
⒈歴史的—体系的理解の教本モデル。このモデルはこれまでの「歴史的教育学」に特徴的な理
解モデルである。このモデルでは理解は①原典資料の確定(対象の秩序づけ)、②原典資料の
分析(対象の要素分析)、③原典資料批判(仮説の検証)とう三つの段階で進む。このモデル
は「解釈学的循環」の最も基本的形式であるとされる。
⒉解釈的理解の統一モデル。ガウスはリッテルメイヤーの理解のプロセス研究を批判的に検
討しながら、理解のプロセスを次の5つの段階に区分している。①科学的な予備的解明。過去
の現実に関して、経験したことをその正確な記述(考古学、文献学、書誌学、伝記、書写の技
法、図像、内容分析、統計的データなどを利用する)によって拡大し、確実なものとする。②
文化的分析。「解釈の理論」として「歴史的文法」の解釈を行う。「歴史的文法」とは、リッ
テルメイヤーがシュライアーマッハーの解釈学の理論の「文法的理解」から援用したものであ
る。すなわち現実の出来事や事物は個々ばらばらではなく、言語を秩序づける文法体系のよう
に、歴史的文化的に一般的な構造の下で関連づけられて理解される。この構造の解明を行うの
が二番目の段階である。③事物における解釈。研究している個人が、個人的・主観的に自身の
生活の実践上の経験を振り返って、先の二つの段階を結びつける段階。「歴史的文法」の諸命

5
題が、現在の日常理解と体験に即して検証される。④自明 (Sich-auskennen)の段階。文化体系の
中で、「解釈と行為のモデル」が通時的にも共時的にも調整されることによって、先の三つの
段階が結びつけられる段階。「歴史的文法」の諸命題が確実に、先行する解釈と行為地平に即
して検証される。⑤異化 (Verfremdung)の段階。解釈のための先取り的な基盤が再び形成される
段階。選択的な解釈の枠組みが発展し、発展した仮説による問題設定を行う。
⒊コンテクスト分析的方法。この方法はランゲヴァントの教育の歴史記述の方法に基づいて
いる。コンテクスト分析は、対象の「理解・解釈・適用」という手順をとるガーダマーの「適
用の解釈学」とは対立するもの、さらにはそれと同様の手順を取ると見なされるディルタイを
始めとする「解釈学的・精神科学的教育学」にも対立するものであり、解釈による「異化」を
基本とする。歴史的陶冶研究の対象は、「異化」や「他者性」の観点で記述されるのであり、
その理解は体系的で構造的というよりも、差異化のたびに多様な解釈を可能にする。したがっ
て、ヘーゲルの歴史哲学が前提にしていたような「歴史的真理」への接近はここでは問題とな
らない。真理要求は「相対化」されて、「歴史的諸科学の言語ゲーム」へと反省的に差し戻さ
れる。すなわち、理解を導いている認識関心とそれに基づいた方法の歴史性それ自体が反省さ
れるのである。そこで問題となるは、歴史的真理への接近よりも、歴史的現実の生成と消失を
競い合う解釈の「移り変わり (Wechselspiel)」を体系的に表象することである。このような特徴
を持つコンテクスト分析を、ガウスは歴史的陶冶研究の方法にとって「最も練り上げられた理
解の端緒」 14と見なしている。そしてこのような理解の基礎づけの可能性として、シュライア
ーマッハーやディルタイの系譜以外の理解概念についての考察を、アナール学派やジンメルや
リッカートの理解概念にまで遡って行っている。そして理解を歴史的陶冶研究の「方法」ない
し「処置」として捉えるのではなく、対象への「アプローチ (Zugang)」の発端となる「解釈モ
デル (Deutungsmusteransatz)」として捉え、実践的に検証していく必要性を説いている。
陶冶概念と陶冶の歴史研究の現代的特徴
これまでの考察において明らかになった陶冶概念と、その歴史的研究の変化の特徴をまとめ
ると次の三点を指摘することができる。
⒈哲学的陶冶概念から経験的陶冶概念への変化。陶冶概念は本来宗教的な意味での「神の似
姿としての自己完成」が、18 世紀に哲学的反省の対象となり、当時学問として成立しつつあっ
た哲学的教育学に取り入れられて、教育学の基本概念として定着していったものである。この
過程で陶冶は多様な観点から(実質陶冶・形式陶冶・陶冶可能性・調和的進歩と発展・関係す
る人間や制度など)考察されるようになっていった。この傾向は 21 世紀の現在まで伝統的に
継承されているが、その間の 20 世紀後半に、陶冶概念は二つの大きな転換点を経ることにな
った。一つは 1960 年代に経験科学と社会学からの両面から、伝統的な陶冶概念(特にシュラ
イアーマッハー、ディルタイの系譜に属する精神科学的教育学)が批判を受け、陶冶概念に経
験的で実証的な観点と社会批判的観点が求められるようになったこと、二つ目は 1980 年代に
特にフランスのポストモダン的哲学の影響を受けて、差異化と多元化の観点から、主体の調和
的進歩による自己同一化という陶冶の伝統的理解そのものが批判されるようになったという
ことである。

6
こうして陶冶概念は、教育学においては 18 世紀以来の伝統的な理解の上に、20 世紀以降そ
の批判を経て、21 世紀の現在には多様な観点で議論されるに至っている。このような変化は、
陶冶の歴史的研究にも当然反映される。従来の教育学における教育の歴史研究(教育史)に代
わって、「歴史的陶冶研究」という名称とともに、陶冶の多様な観点からその歴史が研究され
るようになったのである。その特徴は陶冶の哲学的反省から意図的に距離を取り、社会学の進
展の成果を取り入れながら、人間の社会化の過程と社会構造に注目するものであったり、ある
いは統計やデータ、または写真などの個人的記録も資料にしながら、個人の陶冶の過程とその
成果を多様な観点から、経験的・実証的に考察しようとするものであったりする。歴史的陶冶
研究のこのような傾向は、現在では「歴史的社会化研究」や「歴史的人間学」、個人の伝記研
究や「生活史」研究などの研究上の様々な立場や領域を生み出すに至っている。こうした立場
からは、伝統的な教育史研究では前提とされていた、人間精神一般の調和的な発展、あるいは
陶冶による「普遍的真理」への接近といった伝統的見解は、陶冶概念の反省として批判の対象
となる。
⒉歴史認識の変化。歴史的陶冶研究ではその研究対象の歴史的性格だけでなく、それを研究
する者の観点もまた歴史的に制約されていることを強調する。もちろん教育学の研究対象の歴
史的性格については、すでにディルタイを始めとする精神科学的教育学では前提とされてきた
ことであったが、その歴史認識は精神史や理念史に限定され、社会史や心性史を考慮しない不
十分なものであったと歴史的陶冶研究は批判し、研究対象と研究者の「二重の歴史性」(ヴル
フ)を徹底的に反省しようとする。このような観点からすると、歴史の中に普遍的で絶対的な
真理は認められず、歴史的に相対化された真理があるのみである。また、「人間の全体像」や
「人間の本質」といった見方も歴史的に相対化される。したがって歴史的陶冶研究では、人間
の全体像を求めることを断念し、人間の本質から出発することはせず、人間をその時々の歴史
的前提に依存し、それに制約されながら構成されてきたものとして理解するのである。このよ
うな「構成的で反省的な方法」を発展させ、適用しながら、歴史的陶冶研究はその研究対象や
研究領域を拡大していく。「歴史的教育人間学は、特定の文化的空間や個々の時期に限定され
るものではない。それはそれ自体の歴史性の反省によって、人間諸科学のヨーロッパ中心主義
も、歴史に対する単なる骨董趣味も背後に退かせて、現在と未来に開かれた諸問題を優先させ
ることが原理的に可能になるのである」15。
⒊統一的理解から差異の理解への変化。歴史的陶冶研究の歴史認識の変化によって、研究対
象の理解の方法も変化する。理解の概念はディルタイ以来、精神諸科学の方法論の基礎をなす
ものであった。精神科学的教育学にとって理解は、教育現実を構成している要素(教育学の「基
本的カテゴリー」)を体系的に記述分析して、その構造を明らかにしていくことを特徴として
いた。それゆえこの理解が目指す方向は、最終的には教育現実の構造の統一的な把握であると
言ってよい。それに対して歴史的陶冶研究では、統一を目指した理解ではなく、理解の対象の
「他者性」に注目し、その意味の「差異化」を目指す。教育の歴史は統一的に理解されるので
はなく、多元的に分断され、連続性より非連続性が強調される。「こうして理解のより新しい
処置にとって、古い解釈学とは基本的に異なったいくつの仮定が生じる。すなわち在るのは過
ぎ去ったもの (Vergangenes)であって、歴史 (Geschichte)ではない。最初に在るのは、先行するも
のから後続するものへの永続的流れの中での出来事(Ereignis)なのではなく、ひとつの空間の中

7
で同時的に生起するもの (Geschehen)である。そしてこの空間上での生起は必然的に生じるので
はなく、空間の中で多様に生じるのである。単体の出来事が、目的論的に展開する意義の理想
的な継続性の中で、ないしは構造の諸段階の中で解消されるのではなくて、その唯一無比の特
徴において、唯一無比のコンテクストの中でシステム化されるのである。関与者と出来事の個
別性 (Individualität)があるのではなく、部分的に重なりあう諸現象が固まったもの (Clusterung)
があるにすぎない。時間的継続にそって、何が先行し後続するのか、何が原因で結果なのか決
めることは不可能である。全体性、因果性、継続性、そして意義のカテゴリーは、歴史記述の
ための (historiographisch)研究装置にすぎないのであり、過去の研究対象の中に根づいているわ
けではない」 16。
現代の歴史的陶冶研究から見たディルタイ教育学の批判的検討
以上考察してきた陶冶概念の変化と発展に対応して、従来の教育史から新たな展開を目指す
「歴史的陶冶研究」は、ディルタイを出発点とする精神科学的教育学における歴史的体系的研
究をすでに過去のものと見なし、批判の対象とする。その批判点をディルタイの教育学に関し
てまとめれば、次のようになるだろう。
⒈ディルタイの歴史研究は、普遍史を前提とした理念史研究であり、社会の変化や文化の歴
史、国家や教会などの組織の変遷を、統一的で連続的な観点から記述可能であることを前提と
している。例えばディルタイの教育史研究で言えば、ディルタイは教育史を学問の連続的発展
と、教育が行われる世代や民族の文化状態の盛衰と関連づけて記述しようとしている(Ⅸ
13ff.)。このような歴史観は、歴史の連続性を否定し、歴史の真理を相対的なものと見なす歴
史的陶冶研究の歴史観とは対立し、また経験的で実証的な研究方法を重視する歴史的陶冶研究
の研究方法とも相反するものである。
⒉ディルタイは教育学の普遍妥当性の根拠として、人間の心的生が目的論的構造を内在し、
完全性を目指して発展することを主張する。ディルタイにとって、この心的生の完全性への発
展が陶冶の意味をなしている。心的生の目的論は、ディルタイの教育学だけでなく、彼の精神
科学の基礎づけの研究にとっての基本概念であり、彼の心理学の研究対象でもある。人間の心
的生はすべて内在的な目的論的構造を持ち、この構造全体を前提にして人間の心的生の記述分
析を行っていこうとするディルタイの心理学は、人間の本質を歴史的に構成されたものと考
え、人間の全体性を疑問視する歴史的陶冶研究の見方とは相反するものである。
⒊ディルタイは心的生の目的論的構造の普遍妥当性を前提としている一方で、教育現実の歴
史的制約性を主張する。このようなディルタイの見解は、研究対象だけでなく、研究者の歴史
性という「二重の歴史性」を前提とする歴史的陶冶研究の立場からすると、矛盾したものと見
なされる。歴史的陶冶研究の立場からすれば、ディルタイの教育学において普遍的な心的生の
目的論に基づいた体系的考察の部分(主として知的陶冶に関する部分)と、教育現実の歴史的
制約性(例えば教育理想、教育目的、子ども個人の素質及び才能と職業との出会い、教育制度
や教授体系、教育者と生徒との関係などの歴史的制約性)との関連づけは不十分なままにとど
まっている。精神科学的教育学が「教育現実」の解釈を行うことを特徴とするのであれば、教
育現実の歴史性は徹底的に反省されなければならず、研究対象となる教育現実の個々の事柄

8
は、歴史的経過の中での過去の「出来事」ではなく、その歴史性の反省によって「生起したも
の」として、解釈の対象とされなければならない。こうして教育現実は、「教育―解釈―現実」
17となり、その認識の客観性が普遍妥当性と歴史的相対性の間で問われることになる。
⒋ディルタイの解釈学においては、理解は生と世界の調和的統一を前提としている。このよ
うな理解概念は、世界と歴史の意味の差異化と解釈の多元性を前提とする歴史的陶冶研究の理
解概念とは相対立するものである。この問題はディルタイの教育学の中では、ある時代の文化
体系が時代に応じてひとつの目的論的連関として統一的に把握され、この統一的連関の中で教
育制度が成立するという見解に現れている。詳しく言えば、文化体系は心的生の目的論に条件
づけられており、この意味で「因果的で目的論的な連関」であるとディルタイは言う。それゆ
えある時代の人間類型 (Typ)と、その時代の文化体系の構造は対応関係にある。「教育と陶冶の
文化体系」である「教育制度と陶冶制度」は、このような関係に基づいて発展する。したがっ
て文化体系の因果的で目的論的構造に発展の規則を定めるのは心的生の目的論なのであり、こ
の発展を導く者が教育者ということになる(Ⅸ230)。
ディルタイの教育学に対する上記の四つの批判ないし対立点に関して、われわれはどのよう
に答えればよいのだろうか。まず考えなければならないのは、ディルタイの教育学は主に 1870
年代(ブレスラウ大学教授時代)から 1890 年代(ベルリン大学教授時代)にかけての時期に
講義されたものであり(この間に論文として発表された著作は 1888 年の『教育学論文』のみ)、
ディルタイの思想の円熟期とも言える 1900 年代以降には展開されていないという点である。
次に注意しなければならないのは、彼の教育学は「個別的な精神科学の論じ方の例」18として、
彼が当時構想していた「精神科学の哲学的基礎づけ」との関連で考えられなければならないと
いう点である。すなわちディルタイの教育学は、『精神科学における歴史的世界の構築』(1910
年;以下『構築』と略記 )の中でディルタイが晩年に到達した精神科学の基礎づけの構想の一部、
ないしはその教育学への前倒し的な適用の試みと考えるべきであり、その意味ではディルタイ
の思想全体の発展の中でその内容が検討されなければならない。その上で、その限界と現代的
意義が評価されるべきであろう。
以下において、ディルタイの教育学体系の構想の内容が、精神科学の哲学的基礎づけの構想
の中でどのように進展していったのかを明らかにしよう。その上でディルタイ教育学の歴史的
制約性を明確にした上で、先の四つの批判点からその現代的意義を考えることにする。
ディルタイ教育学の内容構成
ディルタイは、彼の教育学理論の体系の要約とも言える『教育学論文』(1888 年 )の中で、教
育学の普遍妥当性の根拠となる心的生の特徴(内在的目的論・完全性・発展)を述べた後で、
彼の教育学の体系的構想を以下のように明らかにしている(Ⅵ71ff.)。
第一部
教育と教授の起源、学校の起源と、社会の中で分節化が進む学校制度の研究
教育と学校が、社会の外的組織の中心(家庭・地方自治体・国家・教会)に対して持つ諸関係
の研究
(「内側へ進んで」)教育者の創造的能力と、この能力が生徒の素質に向かう関係の考察と記

9
述と分析。
第二部
教育の中で重なりあって生じる個々の諸経過の分析的叙述を、教育を規則化する普遍妥当的な
諸規範の導出としてまとめること。(ただし、知的陶冶に限定される。その内容は、遊戯、感
覚的諸要素の完全な形成、それらの区別と関係づけの発展、興味と注意深さ、記憶、論理的思
考の訓練の分析、現実を代現し、その形態化を可能にする認識の中で行われる表象連関の形成
の分析、教授法が教授諸科目をグループ化し、それらの教育的価値を相互に評価し、その系統
性を定めて、個々の教授対象の方法を確定すること)
以上の研究をふまえた上で、ディルタイは具体的に「目下の国民を動かしている大きな教育
問題」(当時の中等教育の制度改革の問題)を取り扱うためには、次の三つの研究が必要であ
ると述べている。
⒈これまで展開し、規則的に叙述してきた「教育の基本的諸経過」から、一定の文化圏を支
配し、内容を持つ陶冶体系や教育体系や教授体系がいかにして生じてくるのか。
⒉次に、教育体系の比較考察。この比較によって、教育の諸形式が人類の発展が進む中で互
いに結びつけられていることが分かり、限定的ではあるが、教育の発展の中の傾向を定め、教
育制度を導くための科学的洞察が可能になる。
⒊このようにして研究が目下の国民教育制度へ、つまりその歴史と現在へ、その文化への諸
関係の把握へと深化していくことで、ここで全く限定された認識にもとづいて、教育経営の「芸
術的な」作用に対して、国民の学校制度の慎重で継続的な形態化が達成される道を示すことが
できる。
以上のようなディルタイの教育学の構想とその内容の特徴について、次の点が指摘できるだ
ろう。
まず、ディルタイの教育学は歴史的考察と心理学的考察とが密接に結びついていることであ
る。ディルタイは教育学の普遍妥当性の根拠となる心的生の目的論の心理学的記述分析から始
めて、第一部として、教育の理論(教育目的を含む)と制度の歴史的考察から、教育の社会的
機能へと進み、歴史的な教育現実の考察(生徒の陶冶可能性、教師と生徒の教育的関係を歴史
上の教育的天才から記述分析)へと至る。そして第二部として、知的陶冶・心情の陶冶・意志
の陶冶の普遍的な規則性を心的生の目的論に即して導出した後、最終的に具体的な教育改革の
問題に対して、教育体系の歴史的で文化的な比較考察を行い、特定の時代の文化体系から特定
の教育体系の内容が生じる規則性を明らかにすることにより、現実の教育改革に限定した提言
が可能になるとしている。このようなディルタイの教育学の構想は、歴史的考察と心理学(な
いしはディルタイの言う「人間学」)的考察を結びつける試みであり、ノールも指摘している
ようにディルタイの倫理学(1890 年)や詩学(1887 年)、世界観と歴史意識についての考察
(1896−1906 年)も同様の構成を取っている 19。ディルタイの教育学体系を考える場合、まず
これら個別の精神科学の基礎づけに共通した方法上の一貫性(ミッシュは「人間学的歴史的方
法」 (Ⅴ ,L)と呼んでいる)を確認する必要性がある。そしてディルタイの教育学体系に典型的
に現れているこの人間学的歴史的方法が、後の彼の精神科学の基礎づけの研究全体にどのよう
に継承され、進展しているのかが重要なのである。つまりディルタイの陶冶概念の特徴を考え
る場合、ディルタイの思想全体の進展の中でのその位置づけを明らかにしなければならない。

10
この点については、後に詳しく考察する。
次にディルタイの教育学は、実践的な教育改革に向けての教育学理論である。人間学的歴史
的方法を取るディルタイの教育学は、一方では教育史から、他方では心理学からの考察を試み
るが、その結合点である教育現実の具体的な改革がディルタイの念頭にあったことが考慮され
なければならない。彼の『教育学論文』では、次のように述べられている。「今日われわれは
次のような課題に直面している。すなわち、われわれの多様な学校制度の中で、計画性に富む
教育法令を制定すること (Unterrichtsgesetzgebung)によって、個人のそれぞれの能力がそれに応
じた職業への道を見いだすような、学校間の関係を作り出すという課題である。諸民族の競争
の中で、われわれ国民は重大な優位を獲得するであろうし、個々の諸能力を計画的な効率化の
中で言わばうまくやりくりすることで、個々の能力すべてをその最高の働きにまで陶冶し、作
用させることできるであろう。この課題をわれわれの国家の中で解決することは、なるほど確
かに教育法令ではなく、統一的で首尾一貫した学校法令の制定 (Schulgesetzgebung)が必要とな
るだろう。このことはかつてフンボルトとジューフェルン、その仲間による教育改革の実行が
現存の首尾一貫した計画に従って行ったことと同様なのである」(Ⅵ72)。ディルタイのこの
言葉の背景にあったのは、19 世紀後半のドイツの中等教育制度の改革問題であり、具体的には
それは当時影響力を増しつつあった実科ギムナジウム(「実際的陶冶 (Realbildung)」)に対し
て、伝統的なギムナジウムの教育内容(「ギムナジウム的陶冶 (Gymunasialbildung)」)をどの
ように位置づけ、両者を制度的にどのように関係づけるかという問題であったと考えられる。
この問題に関して彼は、1885 年頃に書かれた講演の草稿『中等教育の問題と教育学』の中で次
のように述べている。「実科ギムナジウムが作り出したものが将来どのように評価されようと
も、実科ギムナジウムはわれわれ民族に役立っているのであり、そこでは自然科学と近代語を
最高の陶冶手段とした自由な領域が開かれているのであって、実科ギムナジウムはそれらがな
し得ることを示すだろう。ギムナジウムというドイツ精神の深遠なこの創造物を、われわれは
少なくともより良い時代の中へと生かし続けていきたい」 (Ⅸ79)。ディルタイは理論的には教
育学の普遍妥当性の限界を前提にしながらも、実践的には彼が自らの教育学を当時のギムナジ
ウム改革に結びつけようと考えていたことは注意しておく必要がある。なぜならこの点を見落
とすと、ディルタイの教育学の内容について、シュライアーマッハーの教育学にまで遡る教育
学の理論と実践の関係を、「理論的でアカデミックな教育学」と「歴史的で伝記的な教育現実」
の単なる「緊張関係」としてガウスのように否定的に捉えてしまうことになるからである 20。
ディルタイ教育学における理論と実践の関係
それでは彼はこの理論と実践の結合について、どのようにすれば可能になると考えていたの
だろうか。この点については、すでに述べたように『教育学論文』の最終部分で概略的に言及
されている。それは簡略化して言えば、教育の人間学的歴史的考察(第一部と第二部の成果)
を踏まえて、「特定の時代の文化圏に特有な教育体系がいかにして生じてくるのか」という問
題を、比較法によって歴史的に考察することによって、教育体系に共通の構造とその構成要素、
発展の傾向を導出するというものである。彼のこの計画のより詳しい内容は、『教育学体系の
草稿』(1884/1894 年 )で知ることができる。そこでディルタイは「さまざまな文化圏と文化時代

11
の教育技術の体系の比較考察と、現代ドイツの教育体系に関するこの比較史からの結論」(Ⅸ
229)という題の下に、文化体系は心的生に規定されるので目的論的性格を持つと述べた上で、
この文化体系の目的連関の統一的把握についてまず、認識論的考察を行っている。「ところで
この目的論的連関の中では、展開されたものに従って、目的に向かう努力に統一を与える内実
は、歴史的産物である。この内実は、認識のある段階と、印象と表象と認識を統御する感情の
動き及び衝動の統括の仕方との相関関係の中で成立する。したがってその内容は、統一にもか
かわらず複合的 (complex)である。そのような内容は例えば、18 世紀の人文主義と啓蒙主義の
思想である。複合的で多くの感情を内に含んだものとして、その内容はそれぞれの概念におい
て不十分にしか表現されず、非合理的なものとして決して形式化できないものである。このこ
とは本来的に、認識論的な二律背反なのである。すなわち統一ではあるが、ひとつの概念で表
現できないものである。多くの要因の産物が単一なものでありうるということは、注目すべき
現象である」(Ⅸ230)。この言葉から、ディルタイは文化体系の目的論的連関の統一的把握につ
いて、教育学について講義をしていた当時は、認識論的な基礎づけに困難さを感じていたこと
が分かる。
次にディルタイは、「陶冶と教育の文化体系」の比較のプロセスを次のように述べている(Ⅸ
231)。⒈教育の陶冶目標として念頭に浮かぶ内実について、⒉この内実に与えられている現
実認識と、衝動や心の動きなどの実践的統一との相関関係を分析して、⒊このようにして構造
が条件づけられるので、この構造を比較する。すなわち諸々の陶冶要素の構造の比較(哲学―
修辞学、言語―諸々の実在、外的世界―内的世界)。そしてこの構造の比較から、現在に対す
る構造の発展傾向が明らかになり、現存する政治や社会の体系との関係で、この傾向を批判的
に検証する。つまり、今日の文化体系の中での不変の構成要素を確定する。ここから問題とし
て生じるのは、この確定点から発展の傾向に応じて、確定すべき点と変更すべき点を定めるこ
とである。(この確定点としてディルタイは、国民全体の陶冶、自然科学と精神科学、(学校
制度の)特殊化、人間の諸能力の結合による向上、経済的諸条件などを概略的・断片的に示し
ている。)
以上の考察から、ディルタイの教育学理論は教育学一般の普遍妥当性の限界を主張すること
だけが主眼ではなく、その人間学的歴史的考察により、最終的には実践的問題の解決へと向け
られていることは明らかである。しかしこの最終的な結論部について、現存する教育学関係の
遺稿をみる限り、断片的で概略的なものしか残っていない。このことは、ディルタイが当時の
具体的な教育問題(ギムナジウム改革)に対して、理論的考察においてはおそらくは完全な帰
結にまでは至っていないことを示している。それゆえ、当時の教育改革の問題に対してのディ
ルタイの発言についても、ノールが指摘するような「二面性」 21―時代に即した実証主義的傾
向と伝統的ギムナジウムの維持という傾向―が見られるのであり、このことはディルタイの教
育学が、一方では心的生の目的論の普遍性から、他方では教育の歴史から出発して、教育現実
の具体的問題の解決に向かう途上にあることの反映であるといえる。
教育に対するディルタイの信念
しかし理論的考察が途中であるだけに、当時のディルタイの教育改革に対する具体的で直接

12
的な提言には、彼の教育に対する個人的見解や信念のようなものが表現されており、興味深い。
この点について、いくつか指摘しておきたい。
まず、ディルタイは教育改革の実際的な推進力を教育の実践家(教師)に置いている。彼は
教育体系の比較について次のように述べている。「この処置の目標は目前の体系の形態の実践
的な取り扱いのために、確固とした照準点を獲得することである。実践家の処置が、ここでは
われわれにとってまず模範となる。実践家は、慎重に、洞察力をもって目前の体系を諸々の要
求と調整し、それによって形成し続ける芸術家である。改革が、しかし決して急進的ではない
ような改革の変化が、実践家の処置から生じる成果なのである。彼らの処置を可能な限り意識
化させ、科学的なものにすること、このことが意図されなければならない」 22。さらに教師の
仕事について、次のように述べている。「実際の改革は、教室の中での継続的で困難な教育の
仕事によってのみ達成される」23。「しかも所与の時代と民族の理想は、教師の学級の中に生
きている。したがってそれは合理的には表現できない。教師の技術によってのみ、それは実現
するのである」(Ⅶ271)。これらの言葉に現れているのは、ディルタイの教師に対する深い信頼
と言ってよいだろう。彼が教育学の中で歴史的な「教育的天才」の記述分析を「最も魅力的な
課題」 24と呼び、その「教育愛」を特に賞賛しているのは、歴史上の教育的天才の実践に、現
在の教育改革(彼の言う「急進的ではない改革」)を考える上での模範と解決の可能性を見い
だしているからに他ならない。
次にディルタイは教育を国民教育として捉え、教育改革のための教育目標を規定する要因と
して、諸科学の継続的進歩と、特定の時代の特定の民族の文化状態の二つを挙げている。両者
の関係についてディルタイは次のように述べている。「一方では国民文化に対して、他方では
諸科学の進歩に対して持つ教育の二重の関係から、ヨーロッパの諸々の教育体系における固有
の進歩の仕方が生じ、そして教育体系が一定の時代、つまりわれわれの時代に対して持つ課題
が生じる。教育体系はその根本において、国民的なものである。つまり教育体系の課題は、一
国民を維持する力である道徳 (Sitte)と心情生活と理念世界の確固とした体系を、成長途上にあ
る人間の心情生活の中心へともたらすことである。これによって教育は、民族と国家を維持す
る力となった。教育は一国民の道徳と大きな指導理念と心情世界の没落に対して、力強く抵抗
するのである。しかし他方で諸科学の進歩全体の教育は、個人がその立場とそれにふさわしい
活動のために、可能な限り完全な科学的技術を活用できることに条件づけられている。このよ
うな関係から、教育の最も深遠な課題として生じるのは、理性的判断 (Raisonnement)と科学は
国民道徳と理想という確固とした体系を損なってはならないこと、他方でこれら [筆者注:国民
道徳と理想を ]維持する諸能力は、個人にその最高の能力を与える科学的技術の自由な発展を妨
げないこと、である。両方の要因の調和的均衡に、われわれの世代の真の教育目標がある。世
代のあらゆる能力をその活動のために、専門的な科学的準備によって解き放つこと、しかし同
時にそれらの能力を、その国民を維持する諸力に確実に従属させること、このことはプロイセ
ンにとってまず準備されなければならない、差し迫った教育法令の課題として示されうるので
ある。われわれ国民の指導的立場を持続させるには、部分的にはこの課題の解決にかかってい
る」 (Ⅸ19)。
このようにディルタイによれば、特定の国民文化は個人の生涯と同じように栄枯盛衰を繰り
返す一方で、諸科学は継続的な発展を続けていくものとされる。国民文化の没落を避けるため

13
には、諸科学の発展に基づいた教育内容と教育手段によって、国民文化を維持していくための
道徳や心情、理想が次世代に伝達されていかなければならない。特定の時代の文化における教
育の目標と手段は、このような国民文化の維持と諸科学の発展という両者の「調和的均衡」に
よって決定されるのである(Ⅸ15)。そして国民教育の成果は、生徒をその能力と素質にふさ
わしい職業へと導くことで達成される(Ⅴ72,vgl.Ⅸ197f.)25。ディルタイのこのような観点は、
彼の教育史の講義全体を貫く体系的視点であるととともに、彼が当時直面していたプロイセン
の教育法令の課題解決のために必要な観点でもあったことが分かる。このような観点に、ノー
ルが指摘するような「発生学、人間学、民俗学への好ましくない傾向」 26が窺えるにしろ、デ
ィルタイの教育史の体系的研究が当時の教育改革の実践的課題と結びついていたことをここ
で確認しておきたい。
ディルタイの当時の教育改革問題に対する基本的信念として、三番目に挙げられるのが、彼
の改革案がドイツのギムナジウム教育の伝統に根ざしている点である。前述したように、当時
の中等教育改革において、伝統的な人文主義的ギムナジウムと実科学校、もしくはギムナジウ
ム的教養と実科的教養は対立関係にあり、両者をどのように関係づけるべきかが議論されてい
た27。ディルタイは実科学校の時代的な存在意義を認めつつ、伝統的な人文主義的ギムナジウ
ム教育の必要性を説き、二者択一ではなく、両者の接点を求めて制度及び内容上の改革を模索
している。しかし彼の立場は、あくまでドイツの人文主義的ギムナジウム教育を維持する方向
で発言していることは明らかである。彼にとって人文主義的ギムナジウムの教育の基本思想
は、「より高度な典型として過去から突出している古代民族の言語と文学の研究を通して、自
身の国民的教養 (Nationalbildung)を向上させること」(Ⅸ17)である。古典古代の言語と文学の
研究が、いかにドイツ民族特有の国民的教養を形成していったかについて、ディルタイは次の
ように述べている。「しかしわれわれ国民が、あらゆる領域において堅実に思考できるのは、
古典古代の文法の確実で完全な訓練、つまり感覚的に明瞭であり、論理的に確かであり、決し
て逸脱することのない古典古代の形式の習得に負っているのである。さらに言えばドイツ文化
は、メランヒトンの時代以降、経験主義に対して、ギリシャ精神の美的で知的な心情的状態か
ら唯一離れないことによって、そしてそれによってドイツ文化が、キリスト教の独自の理解を
キリスト教の根源と結びつけた後に、ライプニッツの時代の中で近代の経験諸科学との共同作
業に入ったことによって、われわれに普遍的で歴史的な感覚が生じたのである。この歴史的感
覚は、歴史的現実全体をその中に受け入れ、それによってあらゆる種類の精神的現実を認識し、
正しく評価する非凡な能力を獲得したのであった。このことは、政治的観点の客観性と同じく、
継続的発展に対する感覚においても気づかれることである。われわれのドイツ的教養の最も信
頼できる表現であり、ドイツ的教養を形成するのに最もふさわしい道具が、われわれの人文主
義的ギムナジウムである」(Ⅵ83f.)。この言葉から明らかなように、ディルタイがギムナジウム
改革において最も重視しているのは、古典的教養の習得というよりも、それによって獲得され
る「歴史的感覚」なのであって、この感覚はプロイセン国家の将来的な官僚や法律家の育成に
必要不可欠のものであると強く主張している28。
ディルタイ教育学の歴史的制約性

14
ディルタイの教育学における教師の実践への信頼、国民教育の観点、人文主義的ギムナジウ
ム教育の必要性の強調は、当時の教育改革に対するディルタイの基本的見解を現していると同
時に、彼の教育学理論を特徴づけるものであると言える。ディルタイは普遍妥当的教育学の限
界を指摘し、教育現実の歴史性を主張する一方で、心的生の目的論の普遍性を根拠にして教育
の規則と法則は導出可能であるとしている。この教育の規則と法則はしかし、教育現実での適
用範囲が限られており、当面している教育改革の課題を解決するまでには至らない。教育改革
の課題解決のためには、教育制度や教育体系を歴史的及び文化的に比較する必要があり、この
比較によって教育現実の構造と発展の傾向が明らかになり、課題解決の手がかりが得られると
している。しかし教育改革の真の改善は、学校の教室の中で教師が教育愛を持って行う実践に
よって初めて可能となるので、教師の活動を法規的に拘束することは避けなければならない。
また彼の国民教育の観点は、教育の役割を大局的に国家及び国民性の維持に求めているの
で、教育は社会の機能の一つと見なされ、その結果彼の陶冶概念は、彼の生の哲学の基本概念
である心的生の完全性へ導いていくことから、社会の分業の結果である職業へ生徒の心的生を
導いていくことへと限定されてしまっている。そしてディルタイの陶冶概念は結局、心的生の
完全性を目指すと言っても、その内容はドイツの伝統的な人文主義的ギムナジウム教育を理想
としているものであり、それは彼が教育史の中で述べている古代ギリシャの「パイデイア
(paideia)」(Ⅸ20)、古代ローマの「フマニタス (humanitas)」(Ⅸ71)の精神を理想とするか
らであろう。しかしディルタイは、古典古代の教養を単に伝達するのではなく、これらの精神
の習得を通して彼の言う「歴史的感覚」の育成を念頭に置いていたことは重要である。なぜな
らこの「歴史的感覚」は後に述べるように、「歴史的見方」あるいは「歴史的経験」として、
彼の後の精神科学の基礎づけの進展の中で重要な概念として位置づけられるようになるから
である。
このように見てくれば、ディルタイの教育学は理論的にも実践的にも、未完成であると言う
ことができる。理論的には教育現実の歴史性と心的生の目的論の普遍性が、どのように関係づ
けられるのか、その認識論的基礎づけが不十分であるし、実践的にはプロイセンの教育制度史
まで研究を進めてはいるが、教育改革に対する具体的な提言は、教師の自由な実践への信頼と、
人文主義的ギムナジウム教育の維持を主張するにとどまっている。
しかしわれわれは、ディルタイが教育学を「精神科学の個別の論じ方の例」として位置づけ
ていることに注意しなければならない。前述したように、ディルタイが教育学を体系的に論じ
たのはベルリン大学で講義していた 1890 年代までであり、この事実からだけ見ると彼の教育
学は理論としては、当時普及していたヘルバルトに代表されるような教育学理論に対して、教
育学の普遍妥当性の限界を主張した点に時代的な新しさがあったのであり、実践的には教育体
系の歴史的比較を通しての「急進的ではない」改革を主張するにとどまったという評価になる
だろう。しかしディルタイの教育学を、彼が生涯を通して追求し、結局未完に終わった「精神
科学の哲学的基礎づけ」の個別の例示として捉えると、別の見方が可能になる。それというの
も、彼の精神科学の基礎づけの構想は、教育学が論じられていた 1890 年代には例えば『記述
的分析的心理学の構想』 (1894 年 )と『個性研究への寄与(比較心理学について)』(1895 年)
において、さらには教育学を論じることのなくなった 1900 年代以降では『精神科学の基礎づ
けのための諸研究』(1905−1910 年)や『構築』 (1910 年 )及びその続編の草案などにおいて、

15
明らかに進展しているからである。より詳しく言えば、彼の教育学の基礎づけのための基本概
念である心的生の目的論とこれに基づいた教育体系や教育制度の認識は、教育学理論を端緒と
して、精神科学の基礎づけのために、心的生の「獲得連関」に基づく歴史的世界の認識の問題
へと進展しているのである。このような観点から、ディルタイの陶冶概念を改めて見直すこと
ができるのではないか。以下この問題について考察してみたい。
心的生の目的論の進展
ディルタイは教育学において、心的生の特徴として内在的目的論、完全性、発展を挙げ、こ
れに基づいて陶冶の基本は生徒の心的生を完全性へと導いていくことであるとしていた。ま
た、教育制度が生じる文化体系は心的生に規定されるので、目的論的構造を持つものであるが、
その統一的把握は困難であり、概念的に表現しても不十分さが伴い、認識論的には「二律背反」
的であるとしていた(Ⅸ230)。この見解は『構築』では、心的生の獲得連関とそれに基づく
歴史的な作用連関の把握の問題として、継承され展開されている。
ディルタイは『構築』の冒頭で、精神科学の基礎づけの出発点として、精神科学が扱う対象
とは何かについて考察している。その際、精神科学は自然科学と区別されるが、その区別は前
者は「心的なもの (Psychisches)」、後者は「物的なもの (Physisches)」を対象とするというよう
に単純に区分できるわけではないとディルタイは言う。「私は、以下の基礎づけが心的なもの
と物的なものを区別する観点、これらの表現をどのような意味で用いるかの観点を述べよう。
最も身近に与えられているのは、諸々の体験(Erlebnis)である。これらの体験は今やしかし、以
前ここで私が実証しようとしたように[ディルタイの注:全集第Ⅶ巻所収の『精神科学の基礎
づけのための第 1 研究』を指す]、一つの連関の中にあり、この連関はあらゆる変化の最中に
あっても生の経過全体の中で継続している。この連関を基礎として、私が以前心的生の獲得連
関 (erworbener Zusammenhanng)として記述したものが生じる。この獲得連関は、われわれの表
象と価値規定と目的を包括し、これらの項の結合として成立する。そしてこれらの項それぞれ
の中でも、獲得連関は表象の諸関係、価値評価、目的秩序の固有の結合として存在する。われ
われはこの連関を所有し、この連関はわれわれに常に作用し、意識の中にある諸々の表象と状
態はこの連関に方向づけられ、われわれの印象はこの連関によって統覚され、この連関がわれ
われの情動を調整する。このように獲得連関は常にそこにあり、作用しているが、しかし意識
されることはない。人間がこの連関を抽象によって、ある生の経過から切り離し、そして心的
なものとして判断と理論的論究の論理的主体 (logisches Subjekt)とするならば、このことに対し
て反論はあり得ないとものと私は考える。心的なものという概念の形成が正当化されるのは、
この概念で切り離されたものが論理的主体として、精神科学に必要な判断と理論を可能なもの
にすることによるのである」(Ⅶ80f)。
ここで明らかなように、ディルタイは精神科学の基礎づけの出発点を「体験」におき、この
体験は心的生の「獲得連関」に基づいているとしている。獲得連関の概念は、1886 年にディル
タイが行った講演『詩的想像力と狂気』にまで遡ることができ、これ以降ディルタイの心理学
を特徴づける基本概念として、彼の心理学関係の著作はもちろん、詩学や教育学、そして晩年
の精神科学の基礎づけの構想にも一貫して登場するものである。教育学の普遍妥当性の根拠と

16
なる心的生の目的論と、陶冶概念の根拠となる心的生の完全性への発展は、心的生の獲得連関
の持つ特徴として記述されていることが分かる。
さらに心的生の獲得連関の特徴として指摘されていることは、それが人間個人の「生の経過」
から「抽象によって」切り離された結果、「論理的主体」として判断と理論的論究の対象とな
るということである。こうして精神科学の「心的な」対象が形成されることになる。一方で「物
的な」対象と呼ばれるものは、人間個人の体験から、実践的な目的として抽象化されてくるも
のとして捉えられている。「同様にして、物的なものという概念も正当なものである。体験の
中で諸々の感銘、印象、イメージが生じる。ところで物的な対象とは、実践的な目的のために、
この目的の下に置かれたものであり、それを置くことによって、諸々の印象が構成できるよう
になる。心的なものと物的なものという概念を使用できるのは、それらが人間という事実から
抽象化されたものにすぎないということを、われわれが意識している場合に限られる。それら
は諸々の現実を必ずしも十分に示しているわけではなく、正当的に形成された抽象化にすぎな
いのである」(Ⅶ81)。
こうしてディルタイにとって「心的なもの」と「物的なもの」は、もともと人間個人の体験
から抽象化されてきたものだから明確な区分はできず、両者は「生き生きとした連関」(Ⅶ80)
にあるものとして捉えられる。それゆえ精神科学の対象として、両者の連関を含めた概念とし
て「論理的主体」という概念を用いている。具体的にはその対象として、諸々の「個人、家族、
より広い団体、国民、時代、歴史的運動あるいはその一連の発展、社会組織、文化体系、これ
ら以外で人類全体に属する部分、そして最終的には人類全体」(Ⅶ81)が挙げられている。デ
ィルタイにとって、これらはすべて個々に精神科学の対象となるとともに、それぞれが人間と
いう事実に関連したものであるから、個々の対象すべてが連関したものとして捉えられてい
る。「それらについて語ることができ、記述することができ、それらの理論を展開することが
できる。しかし常にこれらの理論は、人間ないしは、人間的で社会的で歴史的な現実という、
同一の事実に関連している。こうしてまず、これらの一群の科学を、人間という同一の事実に
共通して関連することから規定し、自然科学から区別する可能性が生じる。それに加えて、こ
の共通の関係からさらに、人間という事実内容に含まれている諸々の論理的主体についての言
明を、互いに基礎づける関係が生じる。このような科学の二つの大きな部門、すなわち現在の
社会状況の記述にまで至る歴史研究と、精神の体系的諸科学は、それぞれが互いに必要とし、
それによって確固としたひとつの連関を形成する」(Ⅶ81)。このように精神科学の対象とな
る論理的主体は、個々に理論的考察の対象となるとともに、これらはすべて「人間という同一
の事実」に関連しているので、論理的主体相互の関係づけが生じる。こうして個々の論理的主
体についての体系的研究は、歴史的研究と密接に関連しながら「人間的・社会的・歴史的現実」
全体へと組み込まれていくことになるのである。
精神科学特有の処置としての体験と表現と理解
このように見てくれば、精神科学の対象となる論理的主体は、人間の体験の抽象化を経て個
別に現れ、個別の精神諸科学の理論を形成するとともに、その理論的考察を通して、再びそれ
が生じてきた人間自身と、その歴史的社会的現実全体へと連関づけられるという過程をとるこ

17
とになる。ディルタイはこのような過程を簡潔に「体験・表現・理解」として、精神科学特有
の処置として特徴づけるのである。「精神諸科学の対象として人間が生じるのはしかし、人間
の状態が体験され、この状態が生の表出 (Lebensäußerung)の中で表現され、これらの表現が理解
される限りにおいてである。さらに言えば、この生と表現と理解の連関が含むのは、人間が自
己を伝える身振りと表情と語、あるいは制作者の深遠さがそれを把握する者に開かれるような
継続的な精神的創造物、もしくは社会的形成物の中で人間の本質の共通性 (Gemeinsamkeit)を現
し、この共通性をわれわれに常に直観させ、確実なものとするような、精神の継続的な客観化
だけではない」(Ⅶ86)。このように体験と表現と理解の関係の中でも特に表現は、人間の単
なる身振りや言葉から、芸術作品に代表されるような精神的創造物、さらには法律や国家など
の社会的形成物までも含むものであり、ディルタイはこれらを生の表現として、「生の表出」
ないしは人間にとって共通的なものを現している「生の客観態 (Objektivation)」(Ⅶ146)と呼ぶ。
そしてこれら生の表出を通して初めて、人間は確実な自己理解に至るものであると言う。「心
的で物的な生の統一体は、体験と理解の二重の関係によって自らを知るのであって、現在の中
で自己自身を覚知し (innewerden)、想起の中で過去として自己を再発見する。しかし自己の状
態を確定し、把握しようと努め、注意を自己自身に向けることによって、そのような自己認識
の内観的な方法の限られた限界が現れる。すなわち生の統一体の諸々の行為、固定化した生の
表出、それの他者への作用が、人間に自己自身を教えるのである。こうして人間は、理解とい
う回り道を通ってのみ自己を知る。われわれがかつてあったもの、どのようにわれわれが発展
し、われわれであるものになったのかを経験するのは、われわれがいかに行為し、かつてどの
ような生活計画を立て、ある職業でいかに活動したかということからであり、忘れられた古い
書簡から、われわれについてずっと以前に言われた諸々の判断からである。
簡潔に言えば、理解の過程とは、生を通して自己自身についてその深みまで明らかにされる
ことであり、他方われわれが自己自身と他者を理解するのは、自身の体験された生を自己と他
者の生のそれぞれの表現の仕方の中に持ちこむことによってのみである。このようにして、体
験と表現と理解の連関はいかなる所でも固有の処置であり、この処置によって人間は精神科学
の対象としてわれわれに存在する。精神諸科学はこうして、生と表現と理解の連関に基礎を置
く」(Ⅶ87)。このように体験と表現と理解という精神科学特有の連関によって、人間の生の
個別の自己理解と他者理解が可能になるのであり、これらの個別の理解はまた、人間の歴史的
社会的現実全体に対する価値や目的についての言明を可能にする。ここで特徴的なことは、個
別的なものと一般的なものとの間で、目的形成的な同形的な関係が生じるということである。
「こうしてここには、一回限りのもの、単一のもの、個別のものが、一般的な同形性
(Gleichförmichkeit)に対して持つ特別な関係がある。次にここでは、現実と価値判断と目的概念
についての言明の間で生じる結合がある。さらには単一なもの、個別なものの把握は、それら
の中で、抽象的な同形性の発展と同じような最終的な目的を形成する」(Ⅶ87)。ここでディ
ルタイが「一般的な同形性」、目的を形成する「抽象的な同形性」と呼んでいるものは、心的
生の目的論的構造が、人間の歴史的社会的現実全体への連関へと拡大されたものであると考え
ることができる。
作用連関としての歴史的社会的現実

18
これまでの考察をまとめてみよう。人間の生は体験され、獲得連関としてその抽象化を通し
て、論理的考察の対象となる(論理的主体)。論理的主体は理解の共通性に基づいた生の客観
態として、精神科学の対象となる。精神科学は個々の生の客観態を、理解を通してそれが生じ
てきた生き生きとした体験の連関へと連れ戻し、価値判断や目的形成と結びつけ、ついには歴
史的社会的現実全体の連関を目的論的構造の観点で捉えることを可能にする。ディルタイはこ
のようにして把握される構造連関を、「作用連関(Wirkungszusammenhang)」と名づけている。
「体験と理解の最初の洞察として明らかなことは、これらの中では連関が生じることである。
われわれは連関しか理解しない。連関と理解は互いに対応している。この連関が作用連関であ
る。心的生の統一体、歴史、諸々の文化体系と組織、これらの中ではすべてが継続的な変化の
中で把握され、これらの変化は作用と作用を受けたものである。ところでこの関係は、個人の
構造に従って個人の中で起こるか、あるいは構成的な状況の中で起こるかもしれない。この場
合ひとつの作用連関が、内在的目的論の特徴を持ちうることは、何ら変わらない。なぜなら内
在的目的論は、作用の形式にすぎないからである」(Ⅶ257,vgl.Ⅶ153)。精神科学の対象であ
る生の客観態は、すべてが作用連関の観点の下で把握され、作用連関は個人の中で生じること
もあれば、個人を取り巻く状況の中でも生じることもある。この連関は内在的目的論という特
徴を持つ。そして教育もまた、このような作用連関の下に捉えられるのである(Ⅶ166)。
ディルタイはこのような作用連関の特徴である作用するものと作用されるものとの相互関
係を「生の関係 (Bezug des Lebens,Lebensbezug)」と呼び、その出発点を個人に置く。「生の関
係における働きかけは、把握作用と、価値賦与の中で表現される心的状態、そして目的と財と
規範を設定する中で生じる心的状態という構造連関に規定されている。そのような作用連関の
経過がおこるのは、最初は個人においてである。そして個々人が関係する諸々の体系の交点と
してあるように、これらの体系それぞれが作用の継続的担い手であり、さらにその中で、共通
的なものの財と、規則に従ったその実現化の配列が展開する。そしてそれらの中に、今や妥当
性が無条件に置かれる。こうして諸個人の継続的関係は、その中に発展を含み、この発展の中
で諸々の価値、規則、目的が生じ、意識化され、思考の経過の中で確定される。こうした創造
は、個人においてと同様に、共同体、文化体系、国民においても起こるのであり、自然の諸条
件が常に差し出す素材と刺激の下で、精神科学の中でそれ自体の熟慮へと至るのである」(Ⅶ
154)。ここで注目すべき点は、作用連関が個人の中で生じ、そこから発展する一方で、こう
して発展した作用連関はまた、個人を取り巻く共同体、文化体系、国民として、独自の構造連
関として機能すると述べている点である。「構造連関においてさらに基礎づけられることは、
あらゆる精神的統一体は、それ自体の中に中心があるということである。個人と同様に、文化
体系、共同体それぞれは、それ自体の中に中心点を持つ。この中心点において現実把握、価値
評価、財の生産がひとつの全体へと結びつけられている」(Ⅶ154)。
このようにして作用連関は、個人の心的構造を出発点として、共同体、文化体系、国民へと
発展するとともに、それぞれがまた中心点を持つ構造連関として把握される。作用連関はこの
ような生の関係に基づく「展開であると同時に創造であること」(Ⅶ232)を特徴とするもの
であり、この展開と創造が創りあげる最終的な精神的統一体をディルタイは、「世界」、それ
が属する「時代」、「時期」、最終的には「普遍史」に求めるのである。「ひとつの全体とし

19
ての歴史的世界、ひとつの作用連関としてのこの全体、価値を賦与し、目的を設定するものと
しての、つまりは創造的なものとしてのこの作用連関、そしてこの全体をそれ自体から理解す
ること、最終的には価値と目的の中心を諸々の時代と時期、普遍史の中に置くこと、これらの
観点は精神科学の目指すべき連関として考えられなければならないものである。このようにし
て生の直接の関係、生の価値と目的の歴史的対象への直接的関係は、科学の普遍妥当性への方
向に従って、歴史的世界の作用連関の中の、作用する力、価値、目的、意味 (Bedeutung)、意義
(Sinn)の間で生じるような内在的な諸関係の経験に次第に取って代わることになる。そしてこ
の客観的歴史の土台の上に初めて、未来の予測と、われわれの生を人間の共通目標へと組み入
れることができるかどうか、あるいはそれがどの程度可能なのか、という問題が生じるのであ
る」(Ⅶ155)。このようにディルタイは作用連関の中心を、歴史的世界、時代と時期、普遍
史へと定めていくのは、歴史家の課題であり、こうして定まった「客観的歴史」を土台として
初めて、未来への予測と目標を問うことが可能となるとしている。こうしてディルタイは歴史
的作用連関を、精神科学の客観性の根拠とするのである(Ⅶ138)。教育学の人間学的歴史的
考察において提示された心的生と文化体系の関係は、ここでは歴史的作用連関全体の中へ、内
在的目的論的な構造連関として組み込まれていることが分かる。
作用連関の中心化と生のカテゴリー
ところで作用連関は、生の関係に基づく展開と創造を特徴とするものだから、その出発点は
個人に求めることはできるものの、その中心点はあらかじめ定まっているわけではないとディ
ルタイは言う。彼は作用連関が人間個人の心的生の中心に定まってくる過程を、次のように述
べている。「こうして作用連関はまず最初に、諸々の目的の実現として体験される。少なくと
も最も意識の前景にあるものは、そうである。作用連関に諸々の客体、変化、体験が手段とし
て組み込まれている。諸々の目的から生活計画が、目的相互の連関と手段との連関として生じ
る。このことはすべて、計画を立てる現在において、価値意識、つまり現在的なものが過去の
一連の享楽や幻想などで補われることを前提としている。こうしてこのようなカテゴリー把握
に、過去に即して形成された意味のカテゴリー把握が向かってくる。この意味のカテゴリー把
握において、外的な個々の出来事が内的なものへ向かう関係があり、しかもこの内的なものが
存する出来事相互の連関は、究極的な項から形成されたものではなく、ひとつの中心点に向か
って中心化していくものであり、この中心点に、外的なものすべてが内的なものに向かうもの
として関係づけられている。外的なものは意義を含んだ絶え間ない作用の連続であり、意義が
初めて(統一を創造する)。[括弧は原文のまま]」(Ⅶ249)。
ディルタイのこの言葉から明らかになることは、作用連関の把握は彼が「生の実在的カテゴ
リー (reale Kategorie)」と呼ぶものを用いて行われるということである。すなわち作用連関は個
人においてまず、さまざまな「目的」として意識され、これらの目的が連関してその実現のた
めの生活計画が立てられる。この目的設定は「価値」と結びついているが、この価値意識は過
去の享楽や幻想の想起を通して、補完される。このようにして過去の個々の出来事は、「意味」
あるものとして現在へと作用するのであり、こうして次第に現在の価値意識と将来の目的設定
の連関に組み込まれ、目的達成のための「意義」ある計画として統一される。ここで挙げられ

20
た「目的」、「価値」、「意味」、「意義」、さらには「生」や「体験」、「連関」、「構造」
なども含めて、これらはすべて生の連関に基づき、それを把握するための「実在的カテゴリー」
とされる。これらの中でディルタイがとりわけ重視するものが「意味」である。意味とは「部
分と全体との間で主体に生じるすべての関係」(Ⅶ230)であり、意味が「外的なもの」の「絶
え間ない作用の連続」を初めて「内的なもの」へ、すなわちその中心へと向けさせるのである。
こうして作用連関は、一つの「意義」ある構造連関として統一される。このような過程が「理
解」に他ならない。「これら過去の遺物の把握は、どこでも同じである。すなわち理解である。
理解の仕方がさまざまであるにすぎない。すべてに共通していることは、次のような進行であ
る。決まっていないようで決まっている (unbestimmt-bestimmt)諸部分の把握から進んで、全体
の意義をつかみとることと、この全体から諸部分をさらに確実に定めることが、交互に試みら
れることである。個々の部分が思い通りに理解されないことによって、誤りが明らかになる。
そしてこのことが、諸々の部分をまた満足させるように、意義を新たに定めることを強いるの
である。そしてこの試みは、生の諸々の表出に含まれている意義全体が汲み尽くされるまでず
っと続くのである」(Ⅶ227)。
このようなことからわれわれは、作用連関の中心化とは部分と全体の意味理解を通して、そ
の構造を一定の意義を持つものとして定めることであると言うことができる。そしてこの中心
化は、ディルタイが言うように「決まっているようで決まっていない」。生はディルタイの言
うように、絶え間のない流れとして個人に作用しているが、この作用が体験され、意識化され
るのは、理解が「思い通りにいかない」時である。この時初めてわれわれは、新たな意味理解
へと強いられていくのである。このような過程は「所与の表出から、帰納推論によって、全体
の連関へと理解をもたらすこと」(Ⅶ212)であり、ディルタイはこのような理解を「理解の
高次の形式」と呼んでいる。「理解の高次の形式への最初の移行は、生の表出の通常の連関の
理解と、この生の表出の中で表現されている精神的なものの理解から出発することから始ま
る。理解の結果に、内的な困難や既知のものとの矛盾が生じる場合、理解する者は検証へと導
かれる」(Ⅶ210)。
理解の高次の形式と歴史的経験
このような高次の理解は、すべての生の表出の理解に対して、すなわち他者に対しても、歴
史的遺物に対しても、時代や時期に対しても生じるものである。ディルタイにとって、生は人
間個人に連続的に作用し続ける一連の流れ(「エネルギー」)と見なされ、この流れは高次の
理解によって、全体的連関として構造化されていく。このような構造連関を分析することが、
歴史家と哲学者の仕事であるとディルタイは言う。「ある時代のすべてが意味を持つのは、時
代に基本的方向を与えるエネルギーとの関係によってである。このエネルギーは、石碑、カン
バス、行為と言葉で表現される。また、諸々の国家体制と立法として客観化される。歴史家は
このエネルギーに満たされて、より昔の時代を把握し、哲学者はこのエネルギーから、世界の
意義を解釈しようとする。時代を規定するエネルギーの表出のあらゆるものは、互いに類似し
ている。ここから、さまざまな生の表出において、価値規定と目的設定の統一を認識するとい
う分析課題が生じるのである。そして今やこの方向の諸々の生の表出が、絶対的な価値及び目

21
的設定に押し寄せていくことにより、この時代の人間が含まれる圏域 (Kreis)が閉じられる。つ
まりこの圏域には、対立的に作用する傾向もまた含まれているのである。まさにわれわれは、
時代がそれら対立傾向を刻印づけ、支配的方向がそれらの自由な発展を抑制する様を見てき
た。このようにして時代の作用連関全体は、生と心情世界、生の価値形成と目的理念が関連
(Nexus)することによって、内在的に規定されている。あらゆる作用は歴史的であり、この連関
の中へと入り込んでいく。この連関が時代の地平を形成し、この連関によって、各々の部分の
意味が、時代の体系の中で最終的に規定される。このことが、時代と時期がそれ自体の中で中
心化されるということであり、この中心化によって、歴史の意味と意義の問題が解決されるの
である」(Ⅶ186,vgl.Ⅶ178)。
このようにして作用連関は歴史家と哲学者によって、時代や時期として歴史的に把握され、
人間の心情と価値形成と目的理念の構造連関として、その意義が解釈の対象となる。ここで注
目すべき点は、作用連関の構造は生のエネルギーが意味カテゴリーによって中心に向けられな
がらも、その内部に対立的傾向を含んでいるというディルタイの指摘である。そしてこの対立
から、作用連関の新たな展開と創造が生じるのである。「時代ないし時期の根底には、あらゆ
る対立が以前から存続している。その中で対立しているものもまた、時代それ自体の構造を持
っている。そしてこの創造的なものの中で初めて、生、生の関係、生活経験と思考形成の新た
な関係が始まる」(Ⅶ178)。この指摘が重要な理由は、作用連関の中心化によって構造化さ
れた時代や時期の目的や価値は、その時代に属する人間には絶対的なもののように思われて
も、対立の中から次に新たに展開されて生じてきた作用連関(新しい時代や時期)から見れば、
その目的や価値は相対的なものと見なされることになるからである。ディルタイはこのことを
「歴史的経験 (geschichtliche Erfahrung)」と呼ぶ。「歴史的経験は、そのような無条件の価値、
財あるいは規範が形成されてきた経過をたどることによって、それらの違いについて、生がど
のようにそれらを生み出したのか、しかし無条件の設定はそれ自体、時代の地平の制約によっ
てのみ可能であったことに気づく。歴史的経験はそこから、生の歴史的な十分な表示の中で生
の全体性を見るのである。歴史的経験は、この無条件の設定が互いに調停できない争いである
ことに気づく。それら無条件なものに従うことは、確かに歴史的事実であるが、このことが時
代に制約されない人間の一般的条件に、論理的で必然的に還元されなければならないのか、あ
るいは歴史の産物として見なされなければならないかという疑問は、超越論的哲学の究極の深
みにまで至る問いであり、この深みは歴史の経験領域の彼岸にあり、哲学もまた確かな答えを
そこから得られることはできない」(Ⅶ173)。
ディルタイにとって歴史的作用連関の構造は、確かに目的論的構造を取るが、この構造は対
立を内に含む動的なものとしてあり、展開と創造を繰り返す。それゆえ、構造を把握するため
の目的設定は絶対的なものでなく、時代や時期に制約された相対的なものである。このような
「歴史的経験」を通して、初めてわれわれは生の多面性と全体性に気づくことができる。それ
なしではわれわれは、時代的に制約された価値や目的を絶対的なものと思い込み、それに従属
してしまう。そこからは歴史の新しい創造と発展は見込めない。このような経験は、歴史を研
究対象とする歴史家と哲学者が経験するものであるが、歴史家の関心は作用連関の分析によっ
て時代と時期の構造の特徴を明らかにすることにあり、哲学者の関心は時代や時期を特徴づけ
る価値や目的の普遍妥当性を研究することにある。それでは教育者の関心は、どこにあるのだ

22
ろうか。それはこのような歴史的経験を、成長途上にある生徒に伝えていくことにある。この
点に、ディルタイは当時の人文主義的ギムナジウム教育の存続理由を置いているのである。
高次の理解による個別的なものの理解
ところで、高次の理解は生の連関全体へと進み、歴史的経験を可能にするが、このことに関
連してさらに重要なことは、この生の連関の部分と全体の関係の把握を通して、全体に対する
部分の価値がまた明らかになることである。「理解は常に個別的なものをその対象とする。そ
して理解はその高次の形式では、ある作品ないしは生の中に共に与えられたものを帰納的にま
とめていって、ある作品ないしは人物 (Person)、ある生の関係の連関を推論する。ところが、
われわれ自身の体験と理解の分析の中で、個人は精神的世界において自己価値 (Selbstwert)であ
ること、それどころかわれわれが疑いなく置くことのできる唯一の自己価値であることが判明
した。こうして個人は、人間に一般的なものの一事例としてだけではなく、個別の全体として
も関心を引くのである」(Ⅶ212)。ここでディルタイは、高次の理解が生の連関全体に向か
うだけでなく、人間個人にも向かうと述べている。個人はそれ自身で価値を持つ全体として把
握される。それゆえ高次の理解によって、個人の理解へと進む道が開かれる。「人物の秘密は、
その秘密自体のために、常に新しい深められた理解を試みることを刺激する。そしてそのよう
な理解の中で、人間とその創造物を含む諸々の個人の領域が開かれる。ここに精神諸科学にと
って、理解の最も独自の働きがある。客観的精神と個人の能力が一緒になって、精神的世界を
規定する。歴史は両者の理解に基づいている」(Ⅶ212f.)。そしてディルタイは、生の客観態
の理解が理解の共通性に基づいているように、人間個人の理解も人間一般の理解の共通性に基
づいていると言う。「客観的精神がその中に、諸類型として分類される秩序を含んでいるのと
同様に、人間性の中にもいわば一つの秩序体系が含まれており、この秩序体系は人間に一般的
なもの (Allgemeinmenschliches)の規則性と構造から、諸類型へと進み、この類型によって理解
は諸々の個人を把握する。個人が質的な差異 (Verschiedenheit)によって区別されるのではなく、
心理学的に表現することもできるだろうが、いわば個々の要素の強調によって区分されるとす
れば、この強調の中に個別化の内的原理がある。そしてもしわれわれが、心的生とその状態の
状況による変化 (Veränderung)を個別化の外的原理として、構造の諸要素のさまざまな強調によ
る変動 (Variation)を個別化の内的原理として、この二つの理解をいわば効果的に用いることが
できたとすれば、人間と文学作品と著述の理解は、生の最大の秘密への通路となるだろう」(Ⅶ
213)。
ディルタイがここで述べているのは、個人の心的生は高次の理解によって、その構造(獲得
連関)の類型的把握が可能になるということである。この場合、理解は個人の心的生を取り巻
く状況の変化が心的な構造に及ぼした変化(個別化の外的原理)と、心的生の構造を構成する
諸要素の強調による変動(個別化の内的原理)という、相反する二つの方向があり、両者を共
に活用することで、個人の理解への深遠な道が開かれるという。ディルタイのこのような見解
は、彼の個性心理学や詩学の研究を背景に述べられたものと考えられる。歴史的作用連関の中
心が定まることにより、世界や時代や時期の意義が確定され、その構造連関が明らかになるこ
とは、その世界や時代や時期に生きた人間個人の心的生の構造をも浮き彫りにする。世界や時

23
代や時期とその中で生きている人間個人とは互いに作用しあっているのであり、特定の時代の
価値や目的はその時代に生きる個人の人生計画に影響するが、時にその時代に影響を与え変革
の契機を持たらすような人物が現れる。彼の心的生の構造から生じる能力が、その時代に影響
を与える行為や文学作品、著作を生み出すのである。それゆえ歴史の理解は生の客観態の理解
だけでなく、人間の心的生の理解をも必要とするのであり、特に特定の時代や時期の人間像一
般や、時代に影響を与えた人物の個性理解は重要なものとなる。このことは換言すれば、作用
連関の中心は「決まっているようで決まっていない」が、その中心は時代や時期といった普遍
史だけでなく、国家や文化などの生の客観態はもちろん、時代に生きた人間個人の心的生にも
定めることができるということである。ディルタイにとってこれらはそれ自体で中心を持ちな
がら相互に連関し、全体として一つの作用連関として機能し歴史的世界を形成しているのであ
る。
自己省察としての自伝
高次の理解による歴史的作用連関の把握は、生の客観態の理解を通して、時代や時期の中心
化という普遍史的考察に進むが、それは歴史に影響を与えた人物理解をも含み、この人物理解
はまた個性化の原理として心理学を必要とする。ディルタイにとって歴史研究と心理学研究は
切り離せないものであり、歴史的遺物の研究はそれを作り出した人間の個性理解を可能にし、
個性の心理学的研究は個人の歴史的遺物の理解を可能にする。ディルタイがシュライアーマッ
ハーなどの歴史的人物の伝記研究に取り組み、また自伝に注目した理由もここにある。「自伝
は生の理解がわれわれと出会う、最高で最も有益な形式である」(Ⅶ199)。普遍史的理解が
歴史的作用連関全体の構造把握へ進むとすれば、自伝は作用連関を作り出す個人の心的生の構
造把握へと進むものである。「自伝は自己自身の理解である。しかもここでは対象は、一個人
の生の経過としての生である。しかもここでは体験は、この個別の生の意義を定めるための、
理解の継続的で直接的な基礎である。体験は継続的に移り行く現在として、獲得された心的連
関の部分が生じる連関の項となる。それと同時に新たな部分が、後戻り的に作用するものとし
て、ひとつの作用連関の中でともに想起され作用する項として体験されうる。しかしこの作用
連関は、作用する一つの体系としてそれ自体で生じるわけでなく、現在からのあらゆる作用の
中で、自己を諸々の目的に向かわせる意識なのである。これらの目的がひとつの作用連関を形
成するのであり、そこでは欲求もまた目的をそれ自体の中に含んでいる」(Ⅶ248)。
自伝は人間個人の生の経過を本人自身が表現したものであるが、それは個人のそれまでの人
生の獲得連関の表現である。この獲得連関は既に見てきたように、現在意識される様々な目的
から、過去の諸々の出来事まで遡り、それによって初めて人生の意義と計画が定まっていくと
いう過程を取る。これら一連の過程は一つの作用連関として体験されるのであるが、ただしこ
の作用連関の把握が時代や時期の普遍史的連関の把握と異なるのは、理解の対象が生の客観態
ではなく自分自身の生であり、それは著述という形式で表現されるが、この生の理解は本人が
生きている限り、新たな体験に基づいてその都度新たな解釈の対象となるということである。
このことからディルタイは自伝を、常に更新される「自己省察 (Selbstbesinnung)」として特徴づ
けている。「自伝は自己の生の経過についての人間の自己省察が、著述として表現されたもの

24
にすぎない。そのような自己省察はしかし、個人おのおののある一定の段階で更新される。自
己省察は常にあり、常に新たな諸形式で表出される。自己省察はソロンの詩句にあり、同じく
ストア派の哲学者たちの自己の考察、聖人たちの瞑想、近世の人生哲学の中にもある。自己省
察だけが、歴史的に見ることを可能にするのである。自身の生の力 (Macht)と広がり、生につい
ての熟慮のエネルギーが、歴史的に見ることの基礎である。自己省察のみが、血の失せた過ぎ
去ったものの影に、第二の生を与えることを可能にする」 (Ⅶ200f.)。ディルタイにとって自伝
とは自己省察であり、この自己省察は体験と表現と理解の連関という、精神科学特有の処置に
基づいている。そしてこの自己省察が、「歴史的見方」の基礎となる。この「歴史的見方」が、
ディルタイが伝統的な人文主義的ギムナジウムの教育に求めた「歴史的感覚」に相当するもの
であることは明らかである。古典古代の言語や文学作品を学ぶ体験は、歴史的作用連関の中で
自己自身の生を新たに獲得された連関として、理解し直すことである。このことが、個人の歴
史的感覚を鋭くし、歴史的見方の基礎となり、歴史的経験を可能にするのである。
自伝の陶冶論的意義
ところでこのような獲得連関の体験が、体験と理解を結ぶ「表現」という仲介項を通して可
能になることはとりわけ重要である。自伝において自己省察が可能なのは、それが著述という
表現を経由しているからである。それゆえこの自己省察は、「内観」によって得られるもので
はなく、体験の表現を経由する自己理解である。そしてこの体験の表現の特徴について、ディ
ルタイは次のように述べている。「体験から遡り、体験の中にある構造的諸関係によって心的
連関へと進むことは、そのための条件として私に次のような傾向を示す。すなわち究め難い体
験を汲み尽くすこと、そして体験についての言明と体験それ自体を等しくすることの実現であ
る。この心理学的事実は、もはや説明できないものである。この一致を達成するために必要な
行為を遂行する心的エネルギーは、ただ次の点にある。すなわち、諸々の体験の事態が遡って
常に新たな項を要求するという、本質的に構造的な性状に従って、法則的進行が、この要求に
充足が生じる場合、かつその限りにおいて、ある満足の感情を呼び起こすという点である。こ
の経過の中では価値は、体験をくみ尽くす行為の満足と結びついている以外にはありえない種
類のものである。そこにはまた意志作用もなく、あるのはむしろ、事態それ自体と、この事態
をくみ尽くすことの中に含まれている満足によって、さらに広がっていく連関の項へと引き寄
せられていくことである」(Ⅶ29)。
体験を契機として、体験から心的連関へと進んでいく理解は、この体験を現すのにふさわし
い言明を求める。この過程は体験から自己の生の連関に遡って、新たな部分と結びついた時に
得られる満足感に基づいている。ディルタイがここで述べている「体験の新たな項の要求」の
充足、あるいは「体験をくみ尽くす行為の満足」とは、より正確に言えば、体験を構成してい
る連関が生の流れの中へと拡散していくことではなく、体験された事態から自己の生の関係が
有意味な作用連関として中心を定めていき、この中心化によって定まった意義が的確に表現さ
れた時に得られる満足感であると言える。しかしこの満足感は、体験が生の流れの中でさらな
る連関を要求することによって、その要求が満たされない不満足感に取って代わる。こうして
体験をくみ尽くすことは、際限のない課題となる。「心的連関の把握は、外的な客体の把握と

25
同様に際限のない課題である。しかしこの課題は、諸々の体験に含まれているものを獲得する
ことだけにある。こうして心的対象の実在性が常に所有されると同時に、常に概念的に説明す
ることが試みられる。把握の経過は常に二つの契機をその中に含む。すなわち、概念的なもの
及び判断的なものが体験と一致することに基づく満足と、体験をくみ尽くすことができない不
満足である。このことに関して言えることは、心的把握の誤りは特に、概念形成の一定の方向
で体験の内実をすべて満たすことができるという幻想にあるということである」(Ⅶ32)。心
的連関の把握は、体験の概念化とそれに基づく判断が満足できるか否かによって、進展し続け
る。この進展とともに、心的対象は実在性を得るのである。
われわれはここに、教育学において示されたディルタイの心的生の目的論の思想上の発展を
見ることができる。教育学では心的生は内在的な目的論的構造を持ち、完全性を目指して発展
するものとして特徴づけられていた。それ以降の精神科学の基礎づけの試みの中で、心的生の
目的論は、精神科学の客観性を基礎づける歴史的作用連関に組み込まれ、体験と表現と理解の
関係の中で把握される。内在的な目的論的構造は、意味カテゴリーによる作用連関の中心化へ
と進展し、また完全性への発展は、体験をくみ尽くす試みの中で、体験の概念化と判断に伴う
満足と不満足の交代として、実在感を伴って把握されるものとして捉えられている。
このような心的生の目的論の思想的発展から、ディルタイの陶冶概念を改めて見直してみよ
う。ディルタイの陶冶概念を教育学の中だけでなく、彼の精神科学の基礎づけの構想の進展の
中で位置づけるのであれば、次のような陶冶概念の進展を見いだすことが可能である。彼の教
育学によれば、陶冶は本来成長途上にある者の心的生が完全性へと発展することとして捉えら
れていた。それを意図した計画的な活動が教育であった。今や心的生の完全性への発展は、体
験と表現と理解の関係に基礎づけられ、体験の表現を経由する自己省察へと展開している。こ
の自己省察の典型が自伝である。表現を経由する自己省察は、自己の体験の連関を満足いくま
で概念的に把握し、判断することを強いられる自己理解であり、それによってディルタイの言
う歴史的感覚が磨かれ、歴史的見方が習得され、歴史的経験が可能になるのである。このこと
から陶冶の成果は、国民教育という観点で、個性に適した職業との出会いとして評価されるだ
けでなく、子ども個人の自己省察という観点で、子どもが自己のそれまでの生の意味を解釈し、
独自に表現できることが継続してできるようになることにも求めることができるだろう。その
ためには歴史的遺物の解釈の仕方や解釈の論理の研究、体験の表現の仕方(レトリック)や想
像力が重要な役割を果たすものと思われる。歴史に影響を与えた人物の自伝や伝記、古典作品
の読解が教材として持つ価値もここにある。
現代の歴史的陶冶研究からディルタイ教育学に向けられた批判点に対する回答
これまでの考察において、ディルタイの教育学と陶冶概念の特徴とその歴史的制約制、精神
科学の基礎づけの構想全体の中でのそれらの発展について明らかにしてきた。以上のことを踏
まえて、本論の前半で述べた現代教育学における歴史的陶冶研究の立場から導出された、ディ
ルタイ教育学に対する四つの批判点について考えてみたい。
⒈ディルタイの(教育史も含んだ)歴史研究は、普遍史もしくは理念史研究であるという批
判に対して。ディルタイは確かに「普遍史」という言葉を使用しているが、ディルタイが「普

26
遍史」という場合は、社会組織や文化体系といった個々の生の客観態の理解から、これらが属
する時代や時期といった歴史全体の構造的把握に進むことを意味している。このような考察が
可能なのは、歴史をひとつの作用連関と見なすことによる。ディルタイがここで歴史的考察の
対象としている社会組織や政治組織、文化体系、国民性、時代や時期、これらを結ぶものとし
ての作用連関などは、彼の言う精神科学の抽象化された「論理的主体」もしくは「精神科学的
概念」なのであり、この見方からすれば彼の歴史研究は確かに理念史と見なすことができるだ
ろう。しかしディルタイはこれらの精神科学の諸概念の歴史研究に取り組む一方で、その客観
性や実在性の問題について、心理学と認識論の観点から晩年まで取り組んでいたことを忘れて
はならない。人間陶冶の歴史研究が理念史になることを批判して、事実の経験的で実証的な研
究を重視すべきだという主張に対しては、「精神科学における事実とは何か」がまず問われな
ければならないと答えるべきだろう。ディルタイはこの認識論的問題を、精神科学における対
象把握の問題として扱い、最終的には体験と表現と理解の連関の中で解決されるものと考えて
いたことが予測される。しかしこの問題については、現代の認知意味論の発展なども考慮して、
改めて検討されなければならないだろう。
⒉心的生の目的論が、人間の本質と全体性を定めたものであるという批判に対して。ディル
タイは心的生について、それはあらかじめ定まった構造全体として前提されているものでな
く、歴史的に獲得された連関としてその都度解釈されるものと見なしている。心的生の獲得連
関は歴史的作用連関の中に含まれ、そこで体験と表現と理解を通して、その中心が次第に定ま
っていき、それによって部分と全体の構造が初めて明確になるのである。このような見方から
すれば、人間の本質はまさに歴史的に理解されるのであって、この点から見れば、歴史的陶冶
研究の立場と類似しているとさえ言えるだろう。ディルタイの言う「全体」とは、生の連関を
把握するための彼独自の生のカテゴリーとして、「部分と全体」との関係性において常に捉え
られていることに注意しなければならない。
⒊ディルタイの教育学は研究対象と研究者の「二重の歴史性」を考慮しておらず、その結果
教育現実の認識の客観性に疑問が生じるという批判に対して。ディルタイの教育学は(ノール
が自身の教育学の立場から強調するのとは違って)「教育現実の解釈」を意図していたわけで
はなく、人間学的歴史的考察により、当時の教育改革の課題解決に向かうことが意図されてい
たと考えるべきである。彼は一方では教育目的や教育制度の歴史的比較研究から、他方では心
的生の構造の記述分析からこの課題解決に向けて進んでいったが、最終的には理論的解決には
至らず、教育改革に対しては教師への信頼と、人文主義的ギムナジウム教育の維持の主張に留
まっている印象がある。
しかし教育現実を含む歴史的社会的現実の認識の客観性の問題は、彼の精神科学の基礎づけ
の進展の中で、歴史的作用連関の概念によってディルタイなりの解決に至っていると見なすこ
とができる。作用連関は、心的生から出発し、体験と表現と理解を通して、歴史的な連関とし
て構造的把握を可能にする。この展開と創造の中に、ディルタイは構造的な規則を前提として
置く。それは例えば歴史的社会的現実の中で人間の個性理解を可能にする「個別化の原理」と
して、考察の対象となるのである。
⒋ディルタイの解釈学において、理解は生と世界との調和的統一が前提とされているという
批判に対して。すでに作用連関の把握において明らかになったように、生はわれわれを前進さ

27
せる力として作用するが、それに統一を与えるのは意味である。意味によって、生は部分と全
体に分節化され、作用連関として中心に向けられる。このように作用連関の構造的把握は、ダ
イナミックな運動として捉えられ、その内部にはあらかじめ対立的関係が含まれている。この
対立が新たな生の連関の分節化を促していく。生の連関はこうして展開と創造を繰り返してい
くのである。それゆえディルタイにとって理解は、歴史的陶冶研究の立場とは違って、意味を
単に差異化していくことではなく、生を有意義なものとしてその調和的統一を目指しつつ、生
の連関を生産的に分節化し、客観化することによって個と全体の関係を捉え直すことである。
終わりに
以上ディルタイの教育学について、その陶冶概念を中心に、現代の歴史的陶冶研究の立場と
の比較を契機にして考察を進めてきた。考察の過程において、ディルタイの教育学の心的生の
目的論が歴史的作用連関へと組み込まれていったこと、また彼の教育学が当時の教育制度改革
に向けられていたこと、さらには彼の教育学の歴史的制約性が明らかになった。それでは、デ
ィルタイ教育学の現代的意義はどこにあるのだろうか。彼の教育学は普遍妥当性の問題を扱っ
た教育学の古典として、骨董的価値しかもたないのだろうか。これまでの考察を通して言える
ことは、ディルタイの教育学は決してそのように消極的に評価されるべきではなく、むしろ現
代教育学における歴史研究と陶冶研究に対して、次の点で重要な問題提起を行っているという
ことである。
第一に、歴史の客観的認識とは何かという問題である。ディルタイはこの問題に対して「歴
史的作用連関」という独自の概念で解決を与えようとした。また教育現実を含む歴史的現実の
理解について、体験と表現と理解の連関を、解釈学と心理学の両面から記述分析しようと試み
た。このような思想の展開には、歴史認識を常に普遍妥当性と歴史的相対性の関係の中で捉え、
基礎づけようとするディルタイの一貫した態度(「歴史的意識」)が貫かれている。しかしデ
ィルタイの歴史認識の基礎づけは未完のまま、現代の歴史研究のさまざまな立場に何らかの形
で影響を与えながらも、その内容が十分に検討されることなく現在に至っている。
第二に、自伝に典型的な「表現を経由する自己省察」を、陶冶論としてどのように展開する
かという問題である。自伝が持つ陶冶論的意義については、現在多様な観点から注目されてい
る。一方でディルタイは自伝について、個人が自己の体験の表現と理解を通して、自己の生の
連関を展開し創造していく過程と見なしている。ディルタイのこのような見解を、現在行われ
ている個人の生活史研究や心性史研究の理論と実践に対決させることによって、表現を経由す
る自己省察の理論的基礎づけと実践の可能性について、新たな見解が得られるのではないか。
以上二つの問題については、稿を改めて論じることにしたい。 1 Dilthey,W., Gesammelte Schriften, Bd.Ⅵ , S.70. 以下ディルタイ全集からの引用については、巻数をローマ数字で頁数をアラビア数字で本文中に示す。 2 Bildung の辞書的意味については、以下のものを参照。教育思想史学会編『教育思想事典』、勁草書房、2000 年、528-529 頁。Benner,D./Brüggen,F., Bildsamkeit/Bildung, in : Benner,D./Oelkers,J.(Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik, Weinheim und Basel, 2004, S.174-215. 3 三輪貴美江「Bildung 概念の成立と展開について ―教育概念としての実体化の過程―」(日本教育学会『教育学研究』、第 61 巻第 4 号)、1994 年、11 頁。

28
4 Ehrenspeck,Y., Philosophische Bildungsforschung : Bildungstheorie, in : Tippelt,R./Schmidt,B., Handbuch Bildungsforschung, 3.Auflage, Wiesbaden 2010, S.155. 5 Gaus,D.,Neuere Ansätze des ,Verstehens’ in der , Historischen Biludungsforschung', in : Gaus,D./Uhle,R.(Hrsg.), Wie verstehen Pädagogik?, Wiesbaden 2006, S.50f. 6 Tenorth,H.-E., Historische Bildungsforschung, in : Tippelt,R./Schmidt,B., Handbuch Bildungsforschung, 3.Auflage, Wiesbaden 2010, S.135-153. 7 Gaus,a.a.O., S.52. 8 ガウスによれば「歴史的社会化研究」の立場は、70 年代にヴェーラーとコッカによって、構
造論的な論証に基づいて社会史の記述を行う学派として発展し、1999 年にはゲシュトリヒによ
ってハンドブックが刊行されるまでに至った。それに対して「歴史的人間学」の立場は、ポス
トモダン論争以降流行するポスト構造主義で主張される「生産的に解釈される多様性」を自覚
した学派として発展し(この学派に属する人物として、例えばフーコー、アナール学派、ブル
デュー、ギアーツ、さらにはジンメルにまで遡ることができるという)、1997 年にはヴルフに
よってハンドブックが刊行された。このように両者はそれぞれの立場の理論と方法論を展開し
ているが、ガウスの見解によれば、その研究領域や対象の記述は互いに接近していく傾向が見
られるという。 (Gaus,a.a.O.,S.54f.) 9 Ehrenspeck, a.a.O., S.164. 10 Gerstenmaier,J., Philosophische Bildungsforschung : Handlungstheorien, in : Tippelt,R./Schmidt,B., Handbuch Bildungsforschung, 3.Auflage, Wiesbaden 2010, S.171ff. 11 Ehrenspeck, a.a.O., S.159ff. 12 Ehrenspeck, a.a.O., S.157. 13 Gaus, a.a.O.,S.71ff. 14 Gaus, a.a.O.,S.96. 15 Wulf,C., Zur Einleitung : Grundzüge einer historich-pädagogischen Anthropologie , in : Wulf,C.(Hrsg.), Einführung in die pädagogische Antholopologie, Weinheim/Basel 1994, S.15. 16 Gaus, a.a.O.,S.95. 17 Gaus, a.a.O.,S.48. 18 Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg 1877-1897, Hildesheim/Zürich/Newyork 1995, S.48. 19 Dilthey, Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagischen Wissenschaft(Bearbeited von H.Nohl), 4.Auflage., Weinheim 1961, S.6. 20 Gaus, a.a.O., S.48. 21 Dilthey, a.a.O., S.7. 22 Dilthey, Schriften zur Pädagogik(Besorgt von H.-H.Groothoff/U.Herrmann), Paderborn 1971, S.35. 23 Dilthey, a.a.O., S.121. 24 Dilthey, a.a.O., S.100. 25 Vgl. Dilthey, a.a.O., S.114f. 26 Dilthey, Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagischen Wissenschaft, S.6. 27 このことについては、以下の文献を参照。M.クラウル、望田幸男他訳『ドイツ・ギムナジウム 200 年史』、ミネルヴァ書房、1988 年、100—129 頁。望田幸男『ドイツ・エリート養成の社会史』、ミネルヴァ書房、1998 年、51−158 頁。 28 Dilthey, a.a.O., S.86.